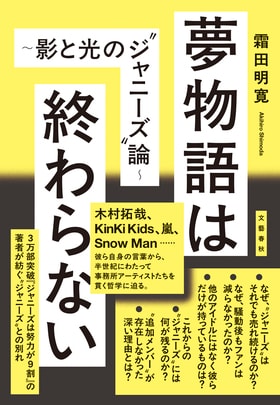外教坊に入ってすぐの頃は、竜笛以外の吹物、弾物、打物と、雅楽に用いられる全ての楽器を一通り経験させられた。果ては舞や歌の手ほどきまで受けさせられ、それまでひたすらに竜笛を自分のものにすることに必死になっていた二人は、大いに困惑したものであった。
だがこれは、先々を見据えてのことであったと後で思い知らされた。
東家のお抱えになったからと言って、そのまま宮中に上がれるわけではない。実際に宮仕えするためには、この上さらに「才試み」という試験に受からなければならなかった。
既に宮廷において楽人として活躍している者達と合奏し、全員からお墨付きを得なければ、その仲間に入ることは決して許されないのである。
取り立てられる前は、同じ楽器を得意とする者の中で一番上手であることが肝要であったが、合奏するとなればそれでは足りない。全体の調和をつくり上げるためには、他を知る必要があった。
伶も倫も器用なほうではあったから、苦しみながらも最初の難関を無事に乗り越えることが出来た。十六歳となった今では、師匠に稽古を受けつつ、東家の下男として働きながら次の才試みを待つ身となっている。
そういった者の中には、いつまで経っても召人になることが出来ず、さりとて自分から諦めることも出来ず、外教坊から出られないまま無為に時間を過ごす者もいた。ただの下男と思って共に働いていた老爺が、外教坊の隅で物悲しく神楽笛を吹いている姿を見つけた時、伶は心底ぞっとした。ああはなるまいと思ったものだ。
そうして、一心不乱に竜笛を奏で、寝る間も惜しんで修業に励んだ挙句――「お主のそれは、俗楽だ」と、師匠に言われてしまった。
楽には魂の色が出る、というのが、師匠の口癖である。
全く同じように育ち、共に励んできた弟と自分。一体どこで差がついたのかと言えば、それはもう、「魂」の差でしかないだろうと伶は思っている。
2025.01.16(木)