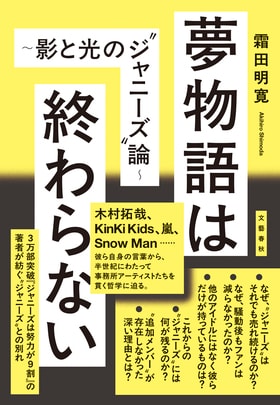別邸でもささやかな花見をするとかで、その道具を本邸から運ぶように命じられたのだった。
諸々の道具の入った漆の箱や葛籠を別邸の敷地に運び入れている最中、思いのほか近い場所で長琴の音がして、心臓が止まるかと思った。
その音色は、浮雲のものにしては拙い。しかしそこには確かに、あの春の夜の音と通じるものがあった。
ついで、手本を示すかのように、滑らかで、手馴れた音が続く。
拙くも明るい調べと、熟練の優しい調べの二重奏に、思わず、涙がこぼれそうになった。
――天の調べだ。
音が止み、きゃらきゃらとした笑い声が聞こえると、もう我慢は出来なかった。
手を動かす下男達に「小用だ」と噓をついて人目を避け、透垣の隙間の大きな場所を探した。辛うじて、覗き見が出来そうな場所を見つけて、目を押し当てる。
前栽の枝葉に紛れ、母親と思しき女はよく見えない。だが、長琴に向かい合う娘の姿は、はっきりと捉えることが出来た。
その面差しは幼いながら、かつて伶が一目見てから、忘れようにも忘れられなかった女の美貌をそっくりそのまま受け継いでいた。
しかし、その髪は風と陽光を受けて、金色に輝いていた。
くるくると靡く特徴的な癖毛は、自分と倫のほかに見たことがない。
母親の、大きく、しかし節ばったところのないたおやかな手が、愛しそうに少女の後れ毛を撫でている。
それに微笑み返す娘の、木漏れ日に輝く清水のようにきらめく瞳。
弟の目だ。
確信した瞬間、全身から力が抜け落ちた。
弟と浮雲の心が確かに繫がっていた証が、そこにあった。
良かった。良かった、本当に。
自分は、心から、あの姫の誕生を喜ぶことが出来る。
今なら認められる。
自分は弟を愛していた。そして、浮雲のこともまた、愛していた。
誰よりも愛しい二人なのに、自分だけはどうしても仲間はずれで、嫉妬して、羨んで、憎んで、でも、それをようやく今、乗り越えることが出来たのだった。
2025.01.16(木)