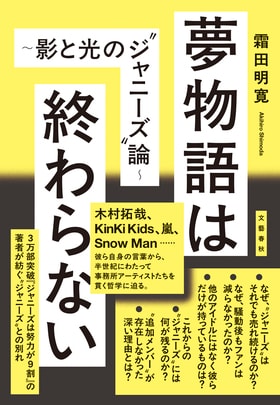「ふしだらで呆れちまうよねえ。アタシだったら、陛下が通って来てくれるんだったら、絶対にそんなことしないよ!」
はあ、と熱っぽく息を吐いた下女を「間違ってもあんたにお呼びはかからねえよ」と下男は鼻で笑う。
伶もそれを面白がるふりをしながら、竜笛に代わって持ち運ぶようになった包丁を静かに腰鞘へ納めたのだった。
――当時、浮雲のもとに通っていたのは金烏陛下だった。
だとすれば、金烏陛下の寵愛を受ける可能性がある状態で、浮雲がほかに愛している男がいると主張しても、周囲は受け容れられなかったはずだ。
しかし、弟と彼女は愛し合っていた。
ひそやかな関係だ。音以外に通じるものは何もなく、二人はふしだらな関係などではなかった。だが、そこには確かに、山神より与えられた才を持つ者同士の連帯があったのだ。
倫は、金烏のお忍びの噂を聞き、浮雲を取られたくなくて忍んでいったのかもしれない。
そして、積年の思いを遂げた。
暴漢に襲われたというのは、おそらく、女房や東家内部の者が浮雲を庇おうとしている主張であって、浮雲自身がそう言ったわけではないだろう。
結果として浮雲は倫の子を宿し――それが東家当主にばれて、倫は殺されてしまった。
だとしたら浮雲の娘というのはもしや、倫の娘でもあるのではないだろうか?
思い至った瞬間、閃くものがあった。
浮雲の娘は、体が弱いという理由でほとんど外に出してもらえないと聞く。それはもしかすると、見る人が見れば一目瞭然なほど、その娘と倫がよく似ているからではないだろうか。
その可能性はある。
浮雲に確認したい。なんとかして娘を、自分の姪にあたるかもしれない少女を見たい。
料理人として働きながら機を窺い、ようやく機会がめぐってきたのは、春になってからのことだった。
浮雲との出会いを、いやおうなしに思い出す季節である。
今年は例年になく桜がよく咲き、東本家の周辺はもったりと重みを感じるような、薄紅色の雲で覆われたようになっていた。
2025.01.16(木)