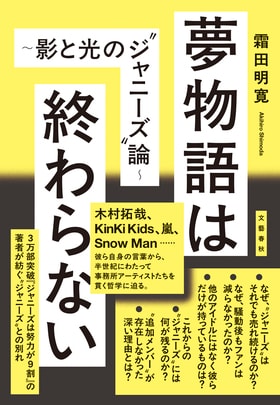――お主のそれは、俗楽だ。
愕然とする伶にため息をつき、師匠は眼差しをその隣へと向けた。
「倫。手本を示してやりなさい」
はい、とどこか戸惑いがちに応えたのは、自分と瓜二つの顔をした弟である。
手馴れた所作で横笛を構え、そして流れ出した音は、師匠が「手本」と呼ぶにふさわしいものであった。
滑らかな音の高低は神楽笛よりも落ち着いており、篳篥よりもしっとりとして、深く豊かな味わいがある。
すうっと空気が澄み、心の臓を直接つかまれたかのように大気が振動するのを感じる。
外から吹き込む風さえもその色を変え、きりきりしていた伶の気持ちすらも、さっとやわらかな羽の先でひとなでされたようになってしまう。
外からの弱い照り返しを受けて、色素の薄い瞳も、伏せられた長い睫毛も、くるくると癖の強い淡い茶の髪も、正確無比に動く指先も、自らが発光しているかのように輝いて見える。
一心に竜笛を奏でる弟の姿は崇高で、美しかった。
自分と弟の容姿はよく似ている。それこそ、見た目だけならばどちらが伶で、倫か、分かる人はほとんどいないはずだ。
だがひとたび竜笛を与えてみれば、その違いはこんなにも明らかだ。
どうして同じ卵から生まれた兄弟で、こんなにも違うのか。
――本当は、痛いほどにその理由は分かっていた。
「気にすることはないよ。裏を返せば、技量は十分だということだもの。あとは気持ちの問題だとお師さまはおっしゃりたかったんじゃないかな」
宴の支度のため、緋毛氈を二人して運んでいる最中のことである。
それほど落ち込んで見えるのかと思うと屈辱ですらあったが、倫は不出来な兄を慰めようと必死で、こちらの思いにはとんと気付いていない様子であった。
「その気持ちが、ついてこないから問題なんじゃないか。俺は、自分に出来ることは何でもやって来たつもりだ。この上、一体何をしろって言うんだ!」
2025.01.16(木)