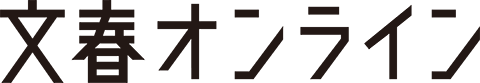韓国映画としてアカデミー作品賞に輝いた『パラサイト 半地下の家族』は、アメリカにおいて、若年のインターネットユーザーが考察やミームで盛り上がっていったポップカルチャー人気の側面があった(参照:【アカデミー賞4冠】“字幕を読まない”米国で『パラサイト』大ウケの2つの理由 | 文春オンライン)。『ドライブ・マイ・カー』の場合、どちらかというと批評家やシネフィルなど、コアなアートハウス映画ファンが中心とされる。
劇中劇『ワーニャ伯父さん』を通し心傷に向き合う主人公
そんな層に刺さったのが、ほぼ映画オリジナル要素である多言語な劇中劇『ワーニャ伯父さん』だ。チェーホフの戯曲に取り組むことを通して主人公が己の心傷に向き合うこの物語は「演技を通してその人の真実があらわになる」現象をとらえる演劇映画でもあるのだ。「芸術の力」を強く感じさせる作品、とも言い換えられる。
であるなら、フィクションや演技に救われた経験を持つ者が多いであろう批評家たちの心を揺さぶり、熱狂を呼んでいったことにも納得がいく。冒頭で紹介したジャスティン・チャンによる推薦文は、以下のように締められている。
〈「『ドライブ・マイ・カー』では、実験的演劇『ワーニャ伯父さん』を中心に最も圧倒的でエモーショナルなシーンが構成されている。
(中略)
(役者が異なる言葉で演じていくような)コンセプチュアルな状況では、本当のコミュニケーションは不可能に思われる。しかし、まるで奇跡のように反対のことが起こり、真実があぶり出されていくのだ。日本語、北京語、韓国語、韓国手話を織り交ぜた会話から、絆が生じ、啓示が花開き、つつましく深遠なアイディアが浮かび上がる。それは、人間として、我々は共通言語以上のもので結ばれており、芸術という言語は、世界共通ということだ。偉大な演劇は、そのことを理解している。偉大な映画も同様なのだ」〉

邦画界は新たな時代へ

言語の壁にとらわれない「芸術の力」を描いた『ドライブ・マイ・カー』は、非英語作品のノミネーションを増やしていっている「新時代のアカデミー賞」の象徴たりえるだろう。
一方、日本はどうだろうか。『ドライブ・マイ・カー』の国際的成功は「日本の映画業界を変える」。それが我々映画人の責任だと語ったのが、同作のプロデューサー、山本晃久だ。ハリウッド・リポーターにおいて「戦後数十年にわたって日本映画が誇った革新性と影響力が失われつつある理由」を問われた彼は、国内市場に依存した結果、日本の観客の好みに合うかたちの進化しか出来なくなった「ガラパゴス」問題を呈している。
資金も少なくチャレンジが拒まれる邦画業界の成功の鍵は、もっと広い世界に向けた映画づくりだという。その成功例こそ、アカデミー賞94回の歴史ではじめて作品賞候補となった日本映画『ドライブ・マイ・カー』にほかならない。アワードが終わったあとも、新たな時代を走り始めた邦画界に注目していきたい。
2022.04.01(金)
文=辰巳JUNK