身体的マイノリティに取材してきた著者だから辿り着いた触覚の哲学
『手の倫理』
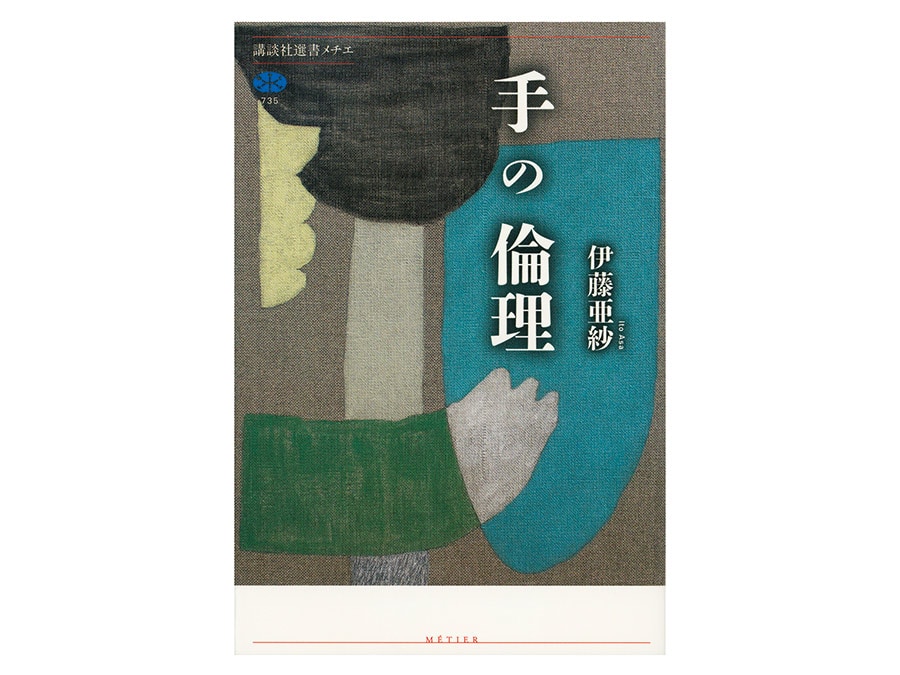
〈触覚の記憶が心をかき乱すのは、それが写真にも映像にも残らない主観的な記憶であり、それゆえ圧倒的なリアリティを保ち続けているからなのでしょう。(中略)その圧倒的なリアリティの中に、当時の人間関係や感情が、時を経て全く古びることなく、真空パックされています〉(「あとがき」より)
モノのように「さわる」ではなく一方的に 「ふれる」でもない「ふれ・あう」に向かって
英語にするとどちらも「touch」だが、日本語には触覚に関する2つの動詞がある。「さわる」と「ふれる」だ。
美学を専門とし、身体や哲学にまつわる横断的研究を行ってきた伊藤亜紗は、新著『手の倫理』でその意味を突き詰め、両者の違いに鋭敏になることで立ち上がる、新たな人間関係の可能性を提示した。
まず冒頭で記述されていくのは、西洋哲学が「まなざし」をモデルに、倫理や人間関係についての考察を積み重ねてきた事実だ。上位感覚として視覚があり、下位感覚として触覚がある。他者に「さわる」「ふれる」触覚は、下級で動物的なものだ、と半ば無視されてきた。
この構図に、著者は異議申し立てを行う。著者はこれまでさまざまな障害を持った方々にインタビューし、身体の不思議さと可能性を追究してきた。
その成果のひとつが、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』だ。つまり、「見(え)る」に縛られない、世界の感覚の仕方を探り続けてきた人なのだ。その経験が、触覚をモデルにした倫理構築のための、大いなるジャンプボードとなった。
自分の身体によって得た「さわる」「ふれる」経験を吟味し、哲学へと昇華するプロセスにも抜群の説得力が宿る。例えば、走ってくる子供を抱きとめる瞬間、〈その子供が腕をすり抜けて再び走りだそうとしているのか、それとも腕の中で安心したがっているのか、私たちは、子供の中にある意思の動きを、その体にふれることによって、感じ取ることができます〉。
視覚や聴覚で得る情報からは感じ取れない、相手の内側にある〈衝動や意志のようなものにふれることができるのです〉。相手を知りたいから、あるいは自分を知らしめたいから、人は人と「ふれ・あう」のだ。
ウィズコロナ時代の新しい生活様式は、人との身体的接触をリスクと捉える。だが、リスクがあるからこそ、ロマンが生じるとも言えるのではないか。自分が過去に経験した「ふれ・あう」記憶のフラッシュバックを味わいながら、今すぐ誰かに手を伸ばしたくなった。
文=吉田大助
CREA 2021年1月号
※この記事のデータは雑誌発売時のものであり、現在では異なる場合があります。




























