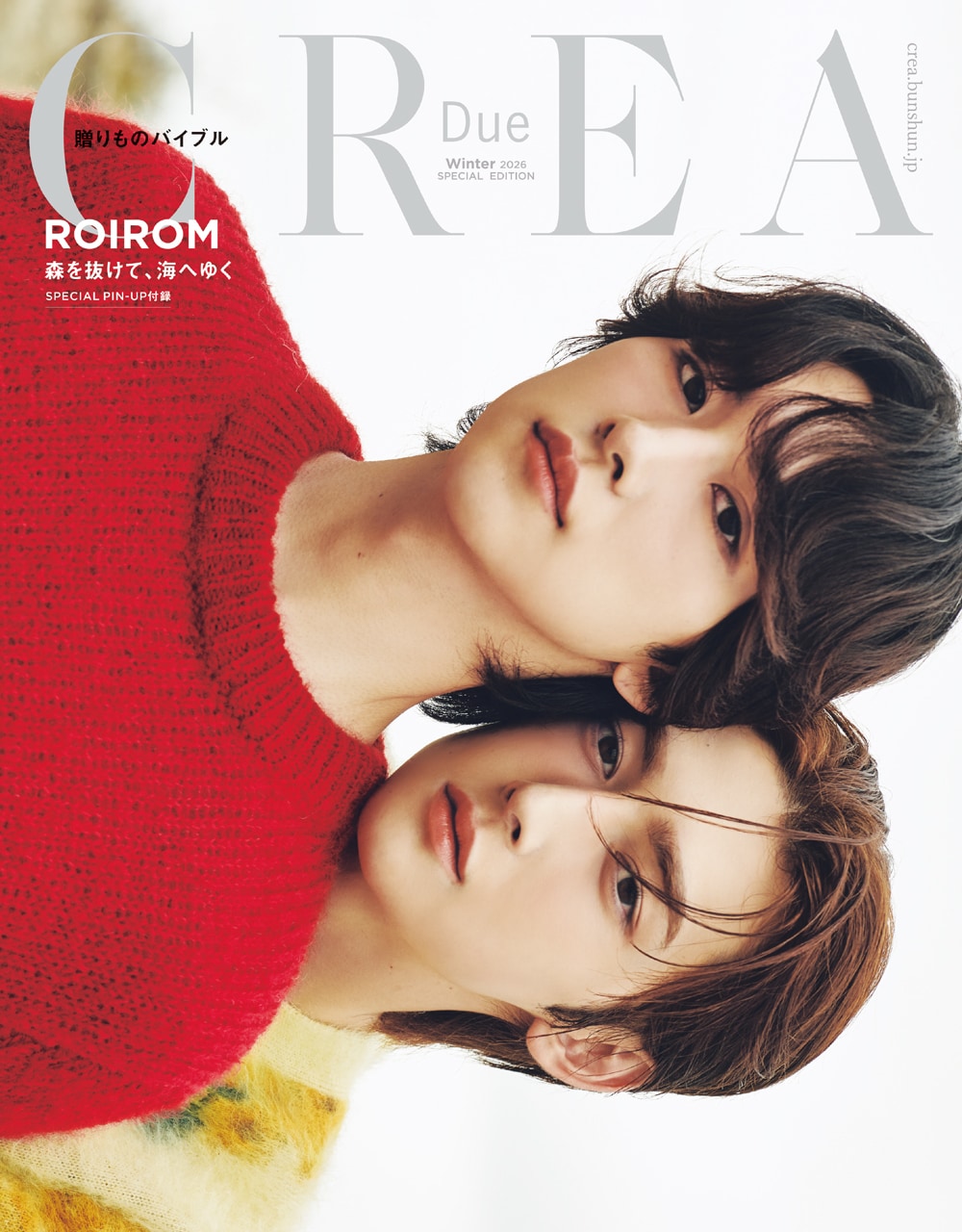3人は一緒に晩活をするようになるが、その際にそれぞれが自分の内面を言語化するような語りを自然とはじめる。これは本当にすばらしい。だって、旧来的な男性の生き方をする人間は、まだまだ感情を言語化せずに生きている人が多いように思うから。
幼い頃から「男性だから」とジェンダーのステレオタイプを内面化し、感情を言語化する機会を奪われた結果、言語化されない感情を抱え、イライラや不満が募り、不機嫌な態度や暴言、はては暴力的な行動に走ってしまう人もいる。
でも、これは現代の「東京の若者」的価値観なのか、本人たち固有のものなのか、この3人は現在、そうならないギリギリを保っている。3人のように自分の感情と向き合い、それを表現する人間になることはよりよい人間関係を築く有効手段だと思う。自分の気持ちを素直に吐くことができ、それを受け止め合う。しかもそれを、女性を介さず男性同士で行っている描写は、この作品の放つ“優しさ”に直結する。
男性同士のケアは必要だけど……
ただ、こうした「男性同士のケア」を、なぜ今描こうとしたのか。そこが引っかかる部分でもある。

もちろん、男性社会が今までに女性にケア労働を押し付けていた文脈を思えば、男性同士のケアは本来、当たり前に行われるべきだと思う。ただ、男性同士のケアを描くのであれば、そもそもケアしなければならない要因となる「男らしさの呪縛」から解放されるところも描く必要があると思っている。それなしに男性同士の連帯を描くと、それは女性蔑視や同性愛嫌悪を含んだホモソーシャル文化の強化につながりかねない。
もし優太らがすでに新しい男性像を身に着け、ホモソーシャルな世界に馴染めていない側の男性であれば、今度はマチズモ(男性優位主義・男らしさ)に対する苦労・嫌悪感があったはず。だが、そういった描写に乏しく、伝わってこないのももどかしい。
現時点で作中で描かれている優太のつらさは、「過酷な労働環境」に由来するものであり、「男であること」に由来するものではない気がする。これは、同僚たちが男女関係なくつらい思いをしている描写からも窺える。しかも、同僚女性のゆい(穂志もえか)は、同じ環境の中で「女性であること」を理由に余計な苦労を強いられている。
プロデューサーになる前も今も、性差の壁や年齢の偏見、モラハラ・セクハラの被害など、ゆいがいろいろなことを経験してきたことは2話で容易に想像できる。優太はまだ男性として有利な立場で恩恵を受けていることを思うと、私は優太よりもゆいの物語を観たくなってしまう。
「コンプラ女王」と揶揄されながらも、古いテレビ業界の体質の中で戦うゆいを中心とする連帯がメインの話ではいけなかったのだろうか。これまで男性キャラクターたち同士の連帯のもと、女性キャラクターたちが分断・対立させられ続けてきたテレビドラマ史の中で、やっと近年増えつつあるシスターフッドドラマ。まだまだそんな作品は作られ続けていいはずだけど、あえてそうせず、今あえて男性同士の絆、友情を中心とするのはなぜだろう。
もちろん「男だってつらい」も認められるべきだけど、それは今やっと叫ばれ始めた「女のつらさ」を「みんなつらい」で相対化、相殺させられてしまうのではないか。インターネット上の「弱者男性論」に利用されるのではないかという危惧もあり、慎重な態度で観てしまう。
- date
- writer
- staff
- 文=綿貫大介
- category