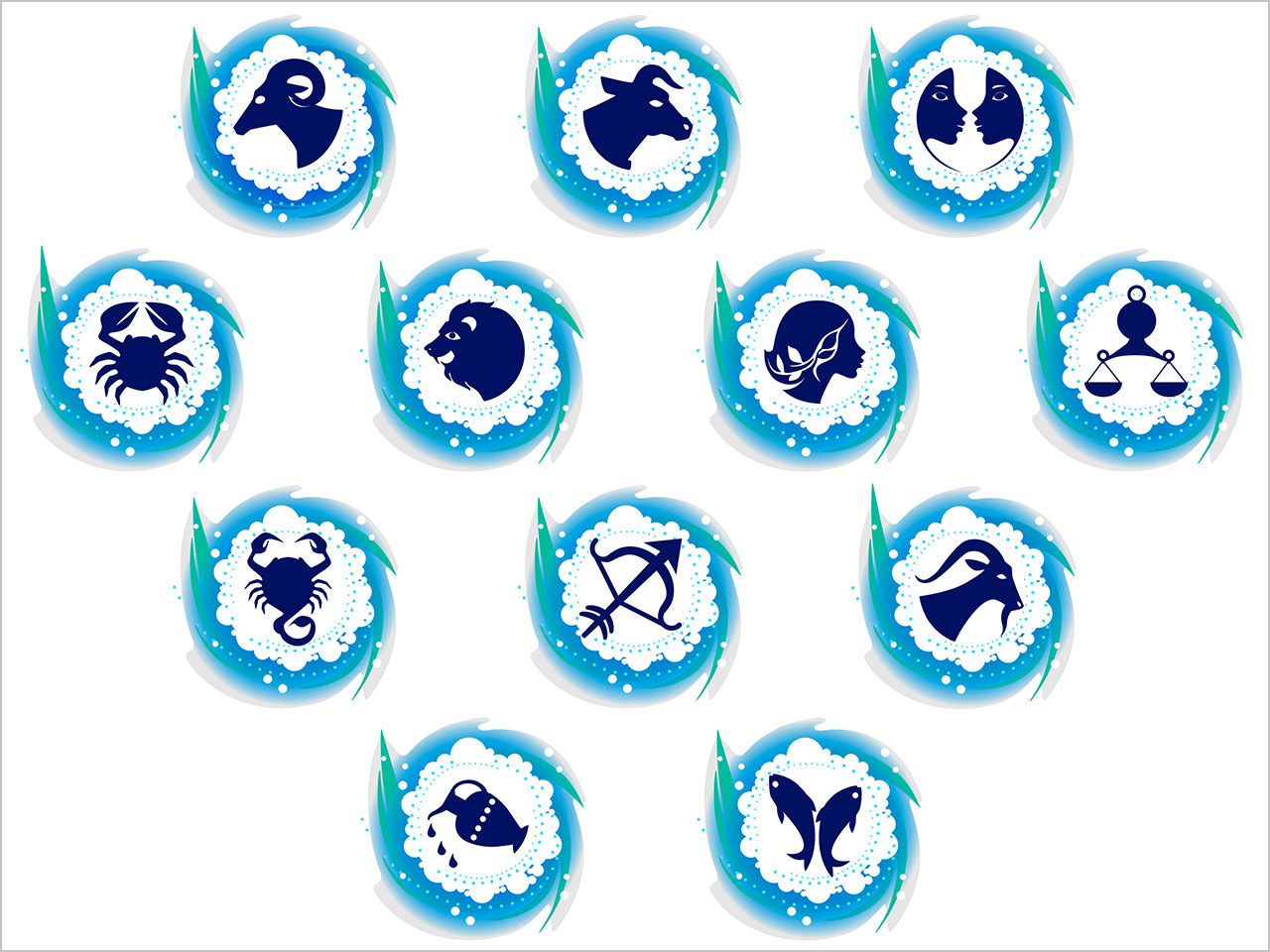映画の影の主人公のような佐野運送の親子
ふたりが、ひとつの荷物を届けてわずかばかりのお金をもらうという過酷な労働環境を映し出すシーンはまるでケン・ローチ監督の『家族を想うとき』(2019年)を思い起こさせる。この映画は、元建築労働者の主人公が、イギリスで配達ドライバーをしていたが、正社員を目指しながらも個人事業主として宅配会社と契約して、毎日の厳しいノルマに苦しめられながら家族を支えているという話だ。
佐野運送には、父と息子以外の家族の顔は見えない(それが逆に家父長制や性別役割分業を感じさせずよかったようにも思う)。しかし、父の昭はこれまでのやりかたが日本を支えてきたと信じたくて、毎日荷物を200個配送していた伝説のドライバー「やっちゃん」を英雄のように崇めるのに対し、息子の亘は、そこまで身を粉にして頑張ったからといって、それが「やっちゃん」に何をもたらしたのか、という後悔を描いていたのが興味深かったし、ぐっと共感させられた。

「やっちゃん」がどんな人なのかは示されない。「やっちゃん」のやってきたことは日本の産業を支える誇り高きことであり、敬い、ねぎらいたいことなのに、同時に経済至上主義の中では、搾取されてきたことを意味していた。だからこそ、社会のシステムが人間の労働力や生きる希望を搾取していることが、誰にでもわかるように示されていた。
こうした現実と重なることがちりばめられている映画は、佐野親子のような登場人物が報われないままで終わることが多いが、野木亜紀子・塚原あゆ子のコンビで作られる、エンターテイメントムービーになると悲しいままでは終わらない。
佐野親子の職業に対する実直な態度が、誰かを救うことになるシーンが描かれていたことに、素直に心を動かされたし、そのことで、彼らが映画の影の主人公のようにもなっていた。
- date
- writer
- staff
- 文=西森路代
- category