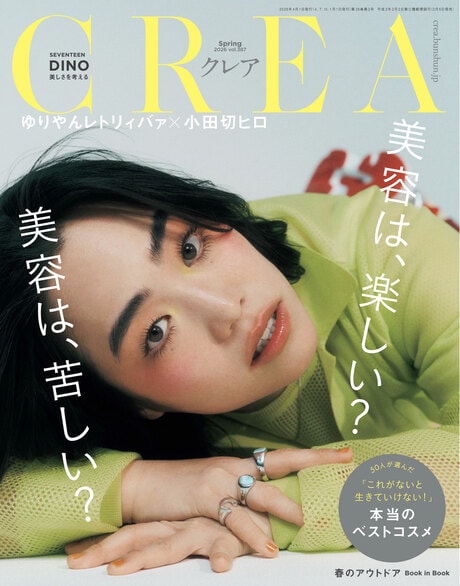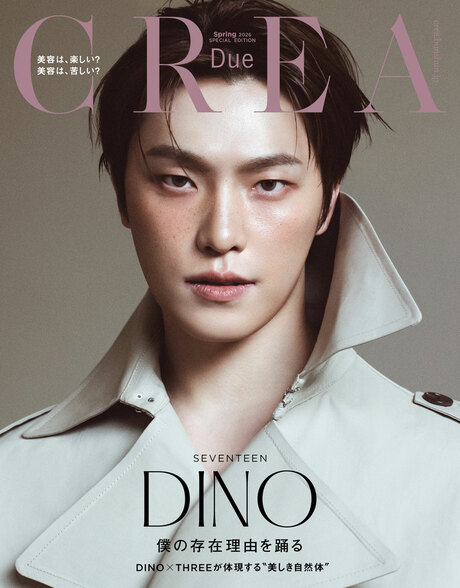世界遺産・国宝の「姫路城」は、今週末の2025年2月15日(土)~3月2日(日)まで、いつもは非公開のエリアが観覧できる、秋冬だけの“特別公開”を開催する。

今回は、城の東に位置する、地形と城郭の構造を利用した高度な防御力を持つ搦手(からめて)周辺を中心に、特別に公開される。そのエリアからしか見られない、穴場の絶景スポットもあるようだ。
今回公開される「搦手道」は、急な坂道にあることから、見学者の安全に配慮して通常は公開されておらず、上から下まで通り抜けができるのは、なんと9年ぶり。

そもそも姫路城は、1993(平成5)年、奈良県の「法隆寺」とともに、日本初の世界文化遺産となった名城だ。国宝でもある姫路城は、白漆喰総塗籠造りの城壁や、大天守と小天守が渡櫓で連結された連立式天守が特徴で、現在の大天守は、1609(慶長14)年に建築された、日本城郭の最高建築。
シラサギが羽を広げたような優美な姿から「白鷺城」の愛称で親しまれ、守りの城として、戦いの備えを意識した仕掛けも多く見ることができる。400年以上が経過したいまも、国内外から多くの観光客が訪れ、魅了し続けている。
そのほか、今回の特別公開の見どころを、写真とともに紹介する。
【との四門】

姫路城の東側に位置する。かつては門の内側に穴蔵(あなぐら)が設けられ、火薬が収蔵されていた。との三門跡から、との四門のエリアは特に紅葉の木々が多く、秋は紅葉の景色も楽しむことができる。
【トの櫓(やぐら)・との一門】

東側と南側に開いている2つの格子窓から、との二門に向けて射撃する必要があるため、窓の下に床板を張って高くし、射撃しやすい工夫がされている。

「との一門」は、姫路城に残る櫓門で白漆喰を塗っていない唯一の門。「昭和の大修理工事」までは白漆喰が塗ってあったが、解体してみると当初は塗っていなかったことが判明したため、元のとおり素木造り(しらきづくり)に戻された。秀吉が自身の権威を示すため、姫路城の北にあった置塩城(おじおじょう)から移築したものであるとの説もある。