
秋の味覚の代表格といえば松茸であるが、悲しいことに私は、味と香りにおいて他の追随をゆるさないともっぱらの噂の、このキノコの王様をまともに味わったことがない。
食べたことがないというわけではない。食べるだけなら、たしかに食べた。それこそ京都の料亭で注文したらいくらになるかわからないぐらい大量の松茸を、一度に……。
二十年ほど前、まだ大学生だった時分に独龍江という中国・雲南省にある峡谷地帯をおとずれたことがある。
独龍江はアジアの大河イラワジ川の源流にあたり、当時はまだ車道が開通しておらず、雲南省側から入域するには峨々たる山峡を幾日か歩かなければ行けない場所だった。
モノの本を読むと、鬱蒼とした密林には毒蛇や毒虫の類がはびこり、マラリアや熱帯性の出血熱が猖獗をきわめている、といったおどろおどろしい紋切型表現がならぶ。
政治的にも中々入域できる場所ではなく、一部の探検マニアから高い注目をあびる“秘境”だった。
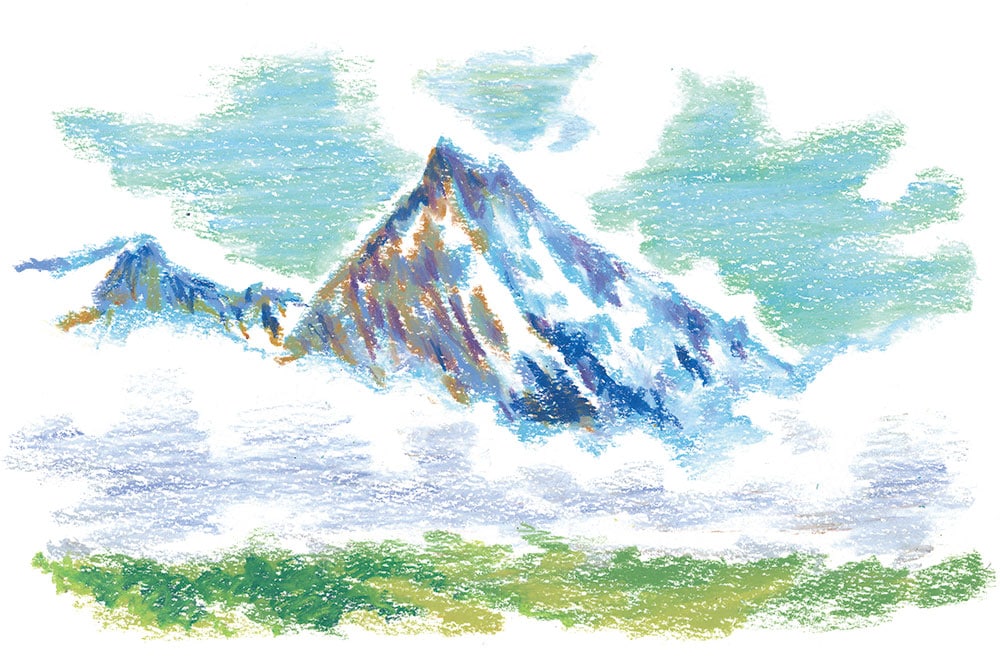
最後の集落を出発した私は、ざわめくような緑の山のなかを黙々と進み、無数の尾根や谷をのり越えた。
独龍江までの山道はたしか二泊三日だったと記憶する。途中に旅人や商人が宿泊するための無人小屋があり、そこで夜をあかした。
無人小屋で横になっていたときのことだ。ダニに咬まれて赤く腫れあがった身体をかきむしっていると、数人の男が無造作に小屋に入ってきて、背中の竹籠をどさっと床におろした。
その中身を見て私は仰天した。籠は大きな松茸でいっぱいだったのだ。
雲南省といえば松茸の産地。彼らが採集した松茸がきっと日本に輸出され、八百屋の陳列台や料理店の皿の上にならぶのだろう。
それにしても首のしっかりした見事な松茸ばかりだ。かぐわしい香りにうっとりしながら身体をぼりぼりかいていると、男たちが籠の中から二十本ほどを取りだし、まな板の上で刻みはじめた。
おそらく、自分でも自覚のないまま、私は光線でも発しかねない目つきでその作業を凝視していたのだろう。火傷しそうな熱い視線に気づいた男の一人が、たまらず私に「食べるか?」と声をかけてきた。答えは書くまでもあるまい。
いったいどんな料理が出てくるのか。お吸い物や松茸ご飯ということはなかろうが、きっと網の上で火で炙りながら焼き松茸にでもするのではないか。
松茸を食べたことのなかった私は、疲労で腹をすかせていたこともあり、生唾をたぎらせて様子を見守った。
ところが、その期待は裏切られた。男たちはおもむろに中華鍋を火にかけると、大量の油を投入し、塩、唐辛子、味の素、豆板醤、ニンニク等々と一緒にジュウジュウと炒めはじめたのである。
皿の上にこんもりと盛りつけられた松茸は、豆板醤で真っ赤に染まり、執拗なまでに火を通された結果、しんなりしていた。口に運んだ私は「好吃!」と声をあげ、一気にがっついた。
たしかに旨い。う、旨すぎる。しかしその旨さは中華料理の旨さであって、松茸の旨さではなかったのである。
それ以来、私は松茸を食べていない。いつか真正松茸料理を食べてみたいと、今年も秋をむかえていつもの夢を見てしまった。
角幡唯介(かくはた ゆうすけ)
ノンフィクション作家、探検家。1976年、北海道芦別市生まれ。早稲田大学卒、同大探検部OB。2016年12月から太陽の昇らない暗闇の北極圏を80日にわたり一人で探検。その体験を綴った『極夜行』(文藝春秋)で'18年、YAHOO!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞と大佛次郎賞を受賞。近著に『極夜行前』(文藝春秋)、『そこにある山‒結婚と冒険について』(中央公論新社)がある。
Column
角幡唯介さんは、開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞している気鋭のノンフィクション作家。これまでに訪れた世界の津々浦々で出会った印象的な人々との思い出を、エッセイとして綴ります。
文=角幡唯介
絵=下田昌克
