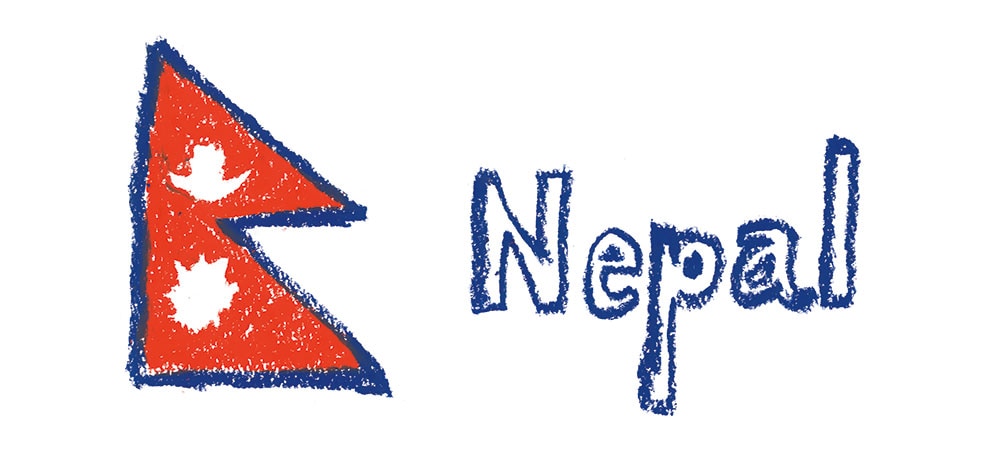
辺見庸が『反逆する風景』の冒頭でこんなことを書いている。
〈風景が反逆してくる。考えられるありとある意味を無残に裏切る。のべつではないけれども、風景はしばしば、被せられた意味に、お仕着せの服を嫌うみたいに、反逆する。〉
辺見庸によれば、風景が反逆するのは、われわれが風景に被せる意味や解釈に対してである。
といわれると、たしかにそうかなと思う。
私たちは普段、風景を見ているわけだが、しかし必ずしもその風景をあるがままの姿でうけとっているわけではない。
私たちの内部に巣くう、なにか決まりきった固定観念とか、思考回路といったもの、あるいは気分や感情を通して風景を整理する。
しかしそうやって整理された風景は私たちの内部のフィルターを通しているので、風景それ自体ではない。
でも風景それ自体はたしかに存在するので、時折、私たちのフィルターを食い破って露出する、とこういうわけである。
たしかに風景はときに反逆する。たとえばチベットのツアンポー峡谷単独探検におもむく途中で見た、あの唐突すぎる光景などは、その典型ではないか。
そのとき私は、とある谷沿いの道の行きどまりにある最奥の村に向かっていた。お供はその手前の村でつかまえた、実直そうな道案内兼荷物持ちの若者一人。
道中、若者が「ちょっと待ってくれ」と言い残し、そそくさと脇の密林に消えた。用便を済ませているようである。
待ちながら私は、こっちの人は紙も水も使用しないが排泄物は何で処理するのだろう、やっぱり葉っぱかな、でも葉っぱで拭くとどうにも残存感が不快なんだよな、とどうでもよいことを考えていた。
と、その直後であった。道の脇の密林のなかに、何やら赤黒いものがぶら下がっているのが見える。
二人で謎の物体のほうに向かうと、五、六頭の豚が縄で後脚をくくられて、太い枝からぶら下がっていた。

豚は熱く乾いた陽に照らされ、不気味にてらてらと輝いていた。ミイラみたいに完全に乾燥して一部は黒く変色している。なんじゃこりゃ、と私は目を剥いた。
豚の丸干し、一頭干し。そういうものが何本かの木々に吊るされているのである。
木々の濃緑と地面の土色から構成される風景全体の色調のなかで、乾燥豚の赤黒さは鮮烈で、ちょっと異様でさえあった。
「何これ?」と私が、おそらく目を点にしながら訊ねると、「ああ、誰かが食べるんだろ」と若者はじつにつまらなさそうな顔で答えた。
何故、私はあれほど驚いたのか。今、写真を見返すとさほど規格外の光景でもないように思えるが、でもあのとき私が、これほど強烈な景色は見たことがない、と呆気にとられたのはたしかなのだ。
それはこの豚の丸干しが、私のその土地に対する意味解釈を屠ったからではないか。
私はあのとき、その土地を踏査の対象としかとらえていなかったのだが、でも現実にはその土地で暮らす人々が生活しており、豚の丸干しを食っているわけで、真実は私の踏査ではなく食われる豚の丸干しにある。
そんな真実が私の虚構を食い破って侵入してきたのかもしれない。
あのときの驚愕は、私の鈍感に対する豚の側からの嘲りだったのだろうか。
角幡唯介(かくはた ゆうすけ)
ノンフィクション作家、探検家。1976年、北海道芦別市生まれ。早稲田大学卒、同大探検部OB。2016年12月から太陽の昇らない暗闇の北極圏を80日にわたり一人で探検。その体験を綴った『極夜行』(文藝春秋)で2018年、YAHOO!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞と大佛次郎賞を受賞。近著に『極夜行前』(文藝春秋)がある。
Column
角幡唯介さんは、開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞している気鋭のノンフィクション作家。これまでに訪れた世界の津々浦々で出会った印象的な人々との思い出を、エッセイとして綴ります。
文=角幡唯介
絵=下田昌克
