
数年前にミクロネシアの太平洋上で操業するマグロ漁船にのりこんだ。
漁に出たまま行方不明となった沖縄のとある漁師について取材をするうちに、一年のほとんどを海上で暮らすマグロ漁師という〈人種〉の〈生態〉に興味をいだき、親しくなった漁船経営者にお願いしたのである。
マグロ漁師といえば腹巻に札束をつっこんで寄港先で酒と女におぼれる、そんな豪放磊落な人々との固定観念をわれわれはもっているわけだが、それはある意味裏切られた。
なるほど、二、三十年前であれば彼らも根拠地のグアムの韓国クラブで金をばらまき派手に遊んだらしいが、それも今は昔。
私が取材した沖縄の十九トン船の漁師にかぎっていえば、近年は売り上げも伸び悩み、ゆえに若者の参入もなく、船長クラスも五十代が若手といわれるほど高齢化が進み、一般船員はみな人件費の安いインドネシア人かフィリピン人ばかりである。
ちょっと寂しい感じのする仕事現場なのであった。
だが、海上での操業現場はやはり壮絶なものがあった。
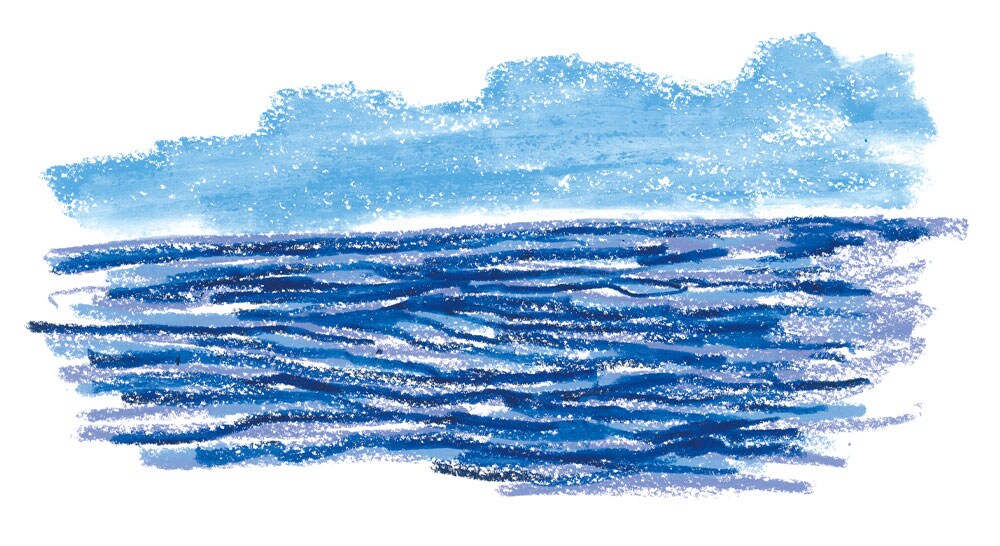
三百六十度、さえぎるもののない絶海のど真ん中で、外国人船員たちははえ縄を次々に回収して、手際よく作業をこなしてゆく。
五、六十キロのメバチやキハダがかかると、すぐさま包丁や特殊な金物をつかって脳天を串刺しにし、腸を引きずり出し、鰓を切り離して、最後にホースとたわしでごしごしと洗浄する。
マグロたちは無言でばちばちと跳ね、絶命し、血の通った生き物から、まるで陶器のようにすべすべ感のある商品に存在の意味を変えてしまう。
血と脂にまみれた現場は凄惨のひと言で、むごたらしい殺戮の臭いがただよっている。そして、その横で船酔いでひっきりなしに嘔吐をくりかえす私……。
何より印象にのこっているのは夜の、しかも嵐のなかでの操業の風景だ。
知らぬうちに積乱雲に突っ込んだのか、船のまわりでは上空で瞬いていた星明りが消え、あっという間に激しい風雨がばちばちと甲板を打ちはじめた。
風で大きなうねりが発生し、大きな白波がどばん、どばんと砲撃のような音を出して船体にぶつかる。
船は大きく揺れて、私の船酔いを悪化させる。しかし船長も船員も作業を中止する気配をみせない。
私は雨具をきて、よたよたと船室を出て梯子をのぼって屋上に出た。
そこで見たのは、闇のなかで黄色くライトアップされた作業現場だった。
風、雨、波がはげしく彼らを叩いているにもかかわらず、船員たちはそれまで同様、てきぱきとはえ縄を回収し、マグロがかかると憐憫の情を一切みせず、機械人間のように無表情のまま止めをさす。
油断すると大波にさらわれそうな危機的な状況に見えるが、それが逆に脳内ホルモンの分泌をうながすのだろうか。
彼らの作業は普段よりもむしろ大胆に、よりスピードアップしているようにさえ感じられた。
嵐のなか、速く、力強く、彼らはマグロを殺しつづける。その残酷な殺しの現場が闇のなかで、やわらかい光に照らされて、コンサート会場のようにぼわーっと浮かびあがる。
私はその風景にある種の美を感じた。それはわれわれの食卓の裏側に秘められた、人間の生の格闘の最前線だった。
角幡唯介(かくはた ゆうすけ)
ノンフィクション作家、探検家。1976年、北海道芦別市生まれ。早稲田大学卒、同大探検部OB。2009年冬、単独でのツアンポー峡谷探検をまとめた『空白の五マイル』で開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞。2016年12月からは太陽の昇らない暗闇の北極圏を80日にわたり一人で探検。その体験を綴った『極夜行』(文藝春秋)で2018年、YAHOO!ニュース|本屋大賞 ノンフィクション本大賞と大佛次郎賞を受賞。新刊に『極夜行前』(文藝春秋)がある。
Column
角幡唯介さんは、開高健ノンフィクション賞、大宅壮一ノンフィクション賞などを受賞している気鋭のノンフィクション作家。これまでに訪れた世界の津々浦々で出会った印象的な人々との思い出を、エッセイとして綴ります。
文=角幡唯介
絵=下田昌克
