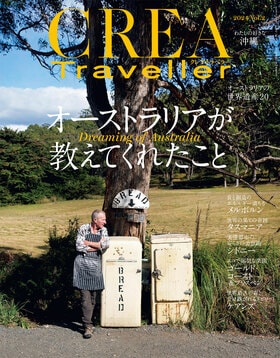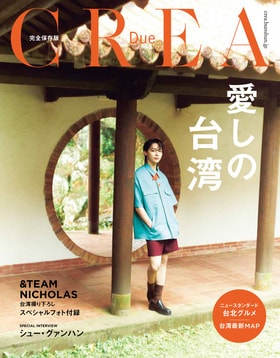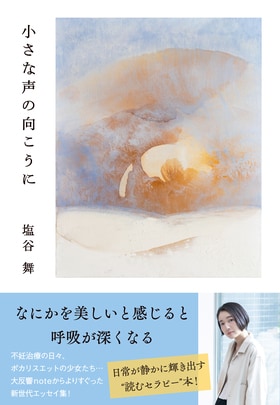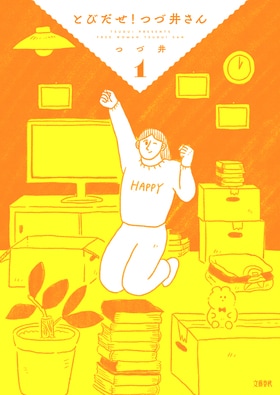〈「大河ドラマの主人公」なのに“悪辣”すぎる蔦屋重三郎の異端な人生 7歳で両親が離婚、吉原のガイドブックで出世、世話になったボスを速攻で裏切る…《主演は横浜流星》〉から続く
蔦屋重三郎は20代後半から30代にかけて、江戸でいちばんの本屋へ駆け上がっていく。
躍進の原動力となったのが黄表紙と狂歌だった。狂歌と黄表紙は戯れの文芸だ。ギャグにおちょくり、洒落、穿ちが散りばめられているだけでなく、世相や政治を揶揄する毒気に満ちている。
江戸の民はそんな黄表紙と狂歌をこよなく愛した。

まず安永4年(1775)に黄表紙『金々先生栄華夢』(きんきんせんせいえいがのゆめ)が大ヒットする。作者は恋川春町、ストーリーは江戸に出てきた田舎者が一代の栄華と零落を一炊の夢にみるというもの。NHK大河のタイトル『蔦重栄華乃夢噺』もこの戯作から拝借したに違いない。
黄表紙は元祖コミックともいえよう。各ページいっぱいに挿絵がレイアウトされ、そこに文章が載っている。春町はこのジャンルの最初のベストセラー作家となり、次いで朋誠堂喜三二が人気を博した。
彼らの成功で江戸の本屋はこぞって黄表紙の出版に力を注ぐようになる。
蔦重だって黙って指をくわえてはいない。
自分の雇い主から根こそぎ出版権を奪う手腕
ただ、黄表紙の勃興期に彼は20代後半に入ったばかり。吉原の細見を売るスタンドみたいな小さな本屋がどうやって戯作界の巨頭とお近づきに?
そのヒントはふたつある。ひとつは細見で培った吉原ネットワーク。春町と喜三二は武家、しかも江戸留守居役だった。この役職、他藩や幕府の情報収集のため吉原にはしょっちゅう出入りする。

「吉原の本屋の蔦重ってのが先生にお逢いしたいといっておりまして」
こう妓楼の主人から持ち掛けられたら、人気作家だって顔くらいは合わせてくれただろう。
もうひとつは、蔦重を吉原細見の編集スタッフとして使っていた鱗形屋孫兵衛のルート。
2024.01.07(日)
文=増田晶文