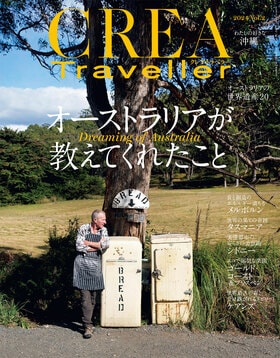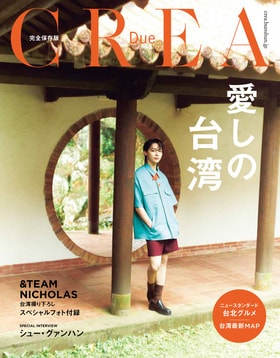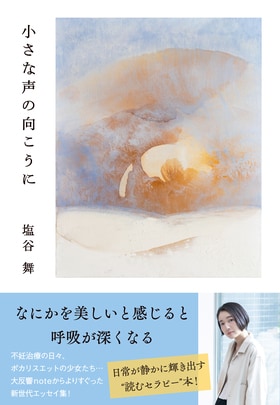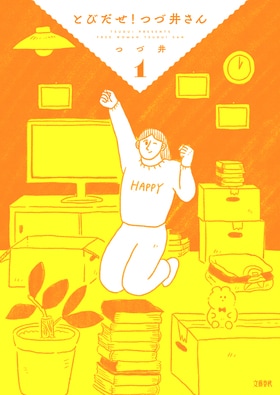第三章「人権問題の争点化」では、一九六〇年代末から一九七〇年代初頭にかけ、台湾で行われている抑圧的な政治に、日本がどのように関与していたのかを確認する。当時の日本国内には蔣介石政権の統治に反発する台湾出身者も在留していたが、そのなかには、中国とは別の独立した国家を台湾に建設することを目指した「台湾独立派」の人びとや、台湾が中華人民共和国と統一される未来を望んだ「親人民共和国派」の人びともいた。それを踏まえ、日本における台湾に対する関心は、どのような社会情勢を背景にして高まっていったのか検討したい。
第四章「大陸中国との交流拡大と民主化」では、一九七〇年代から二〇〇〇年代半ばにかけての、台湾をめぐる国際情勢および台湾内部の政治変動について論じる。七〇年代にアメリカ政府が対中接近政策をとり、七九年に両国が国交を樹立すると、共産党の対台湾政策も大きく変化した。国際情勢の転換を背景に、台湾では政治の民主化をはじめ多方面にわたる変革が進展し、二〇〇〇年代には民進党と国民党が政権を争う構図が生まれる。その新たな政治情勢はどのような経緯をたどって形成されたものなのか、時系列に沿って確認したい。
第五章「アイデンティティをめぐる摩擦」では、二〇〇〇年代後半以降の台湾政治の推移を見る。一九七〇年代以来の政治変動にともない、二〇〇〇年代半ばには共産党と内戦を戦っていたはずの国民党が共産党との融和路線を打ち出すという「ねじれ」が発生するにいたった。一方、選挙による競争が定着した台湾において、国民党は有権者の「台湾」という土地への愛着や、「台湾人」としてのアイデンティティにも常に配慮する必要がある。そのような状況下、台湾にとって「私たちの歴史」はどのようなものであり、そのなかで「中国」および「日本」という要素をどう位置づけるかは、とりわけ論争的な問題となってきた。歴史問題を含め、近年の台湾におけるアイデンティティをめぐる複雑な様相について、いくつかの事例から見ていきたい。
最後に「おわりに」では、台湾をめぐる近年の動向について簡単に確認したうえで、本書の議論を総括し、今後の台湾を見ていくうえで筆者が重要だと考える論点について整理したい。
「はじめに」より

台湾のアイデンティティ 「中国」との相克の戦後史 (文春新書 1434)
定価 1,210円(税込)
文藝春秋
» この書籍を購入する(Amazonへリンク)
2023.12.15(金)